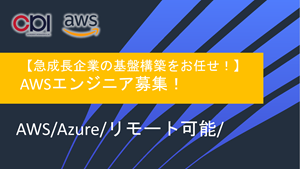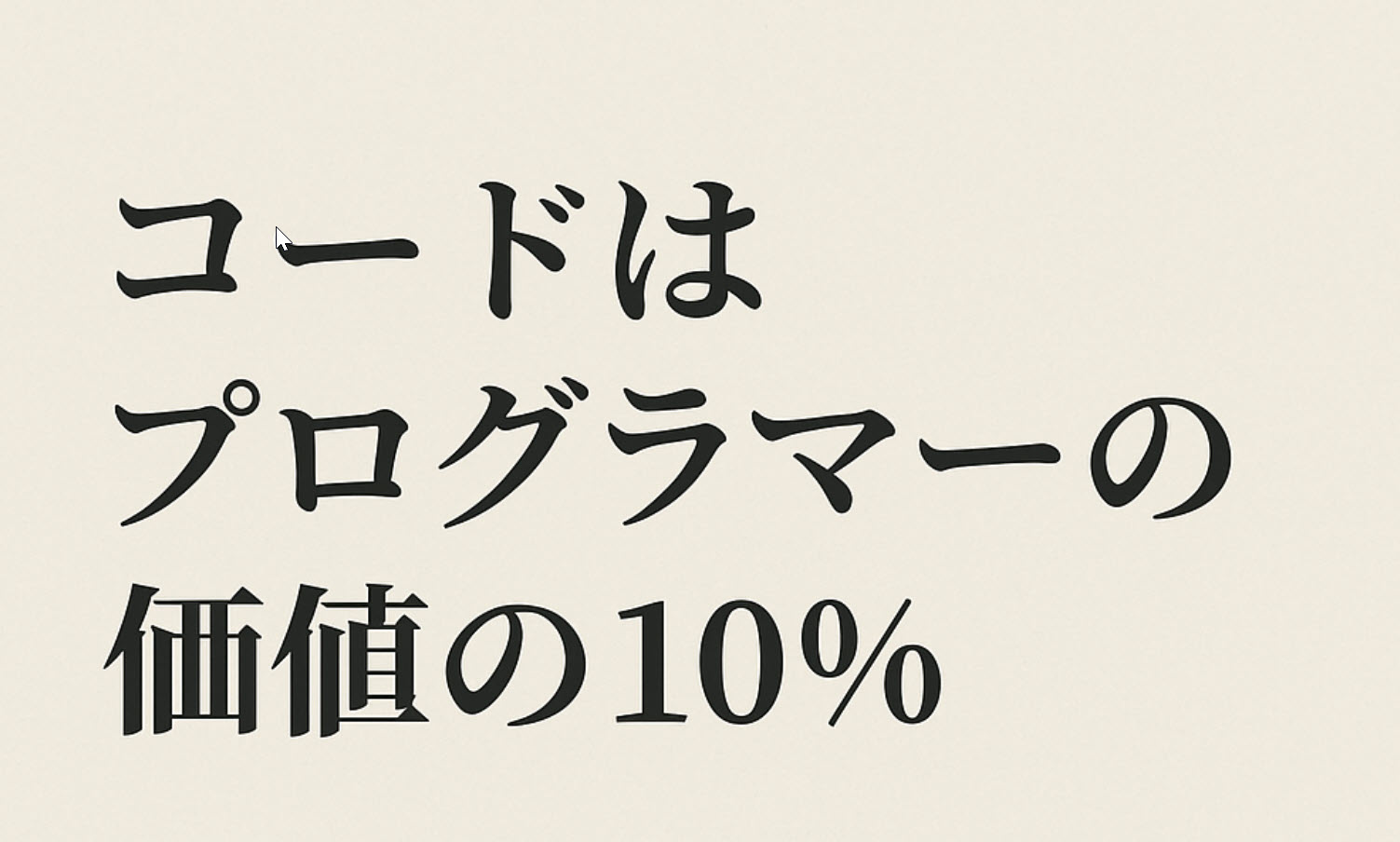はじめに
こんにちは、松山です。
先日、 OpenAI のエンジニアによる講演を聞きました。
話の内容が進むにつれ、静かに衝撃を受け、最後には背筋が少し寒くなるような感覚を覚えました。
講演者は OpenAI の整合性チームに所属する Sean Grove さん。
彼はこう語っていました。
「私たちは長年、自分の一番価値のある成果は“コード”だと思い込んできた。
でも、実はコードはただの“中間産物”にすぎない。」
コードの前にある「構造化されたコミュニケーション」
本当に価値を生むのは、コードを書く前にやっていること。
問題を理解し、人と話し合い、目標を分解し、設計を立て、意図を伝え、そしてそれが本当に伝わったかを確認すること。
Sean さんはそれらをまとめて「構造化されたコミュニケーション」と呼んでいました。
印象的だったのは、次の一言です。
「コードはあなたの意図の“損なわれた投影”にすぎない。」
言葉を聞いた瞬間、心の中で少し震えました。
思い返すと、これまで多くのプロジェクトで、最初の段階からつまずいた原因の多くは、
「ちゃんと伝わっていなかった」ことだった気がします。
みんな同じ理解をしていると思い込み、実は誰も正確に共有できていなかった。
そして完成してから「こんなはずじゃなかった」となる。
──そんな経験、私自身にもいくつもあります。
AI がコードを書く時代に、人は何を残せるのか
以前なら「コードを書くこと」が一番のスキルだと信じていました。
でも今は、AI がかなり正確にコードを書けるようになっています。
疲れもせず、文句も言わず、仕様変更にもすぐ対応できる。
では、人間の価値はどこにあるのか。
Sean さんの答えは、「残りの90%」、つまり構造化されたコミュニケーションの中にあるというものでした。
彼はこう言いました。
今、多くの人が prompt を使ってモデルにコードを書かせているけれど、
その prompt 自体はすぐに消えてしまい、残るのは生成されたコードだけ。
それは、まるで家を建てた後に設計図を燃やしてしまうようなものだと。
本当に残すべきなのは、意図──つまり prompt や、さらに上位の概念である 仕様(Specification) なのだと。
「仕様」とは、意図の言語化
Sean さんの言う「仕様(Specification)」は、
製品ドキュメントほど堅苦しくないけれど、prompt より明確なものです。
「何を望むのか」「なぜそう設計するのか」を文章で記したもので、
理解され、議論され、検証され、そしてときに AI にも再現できるような形です。
一番心に残った言葉
講演の最後で、彼はこう語りました。
「これからの時代に最も優秀なプログラマーは、
意図を明確に表現できる人になるだろう。」
プログラマーに限らず、
プロダクトマネージャーでも、デザイナーでも、運営でも、
自分の考えを丁寧に“言葉”として整理できる人が、
AI と最も自然に協働できるのだと感じました。
もし意図が曖昧なら、AI はあなたの頭の中を「推測」するしかない。
そして、その推測が外れたら、やり直すのは結局人間。
それは結構つらいことです。
私自身の気づきとして
この話を聞いて、「AI は技術職を奪う」と言われるけれど、
本当のところは、「思考を整理できない人」の仕事を奪っていくのかもしれない、
と感じました。
最近、周りのエンジニアが自分の prompt をナレッジベースとして残すようになっています。
プロダクトデザイナーの友人も、仕様書のような形で意図を整理してから AI に試作を頼んでいます。
これは“未来の話”ではなく、もう“現在進行形”の変化です。
最後に、個人的なまとめとして
これは誰かへのアドバイスというより、自分へのメモのようなものですが、
私はこの講演をきっかけに、少しだけ意識を変えたいと思いました。
- prompt を書くときは、結果よりも意図を明確にすること。
- 良い prompt や設計書を残しておくこと。(あとで振り返ると必ず学びになる)
- 構造的に伝える練習を続けること。
AI と共に働く時代、残るのは「自分が何を求めているのかを言葉にできる力」なのかもしれません。
私もまだ全然できていませんが、少しずつ意識していきたいと思います。
終わりに
もし将来、AI が 90% のコードやコンテンツを作れるようになったとしても、
人に残される理由はきっと一つ。
自分が何を求めているのかを、はっきり伝えられるかどうか。